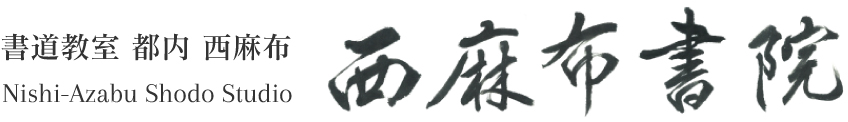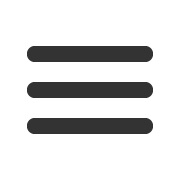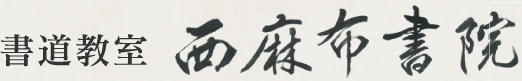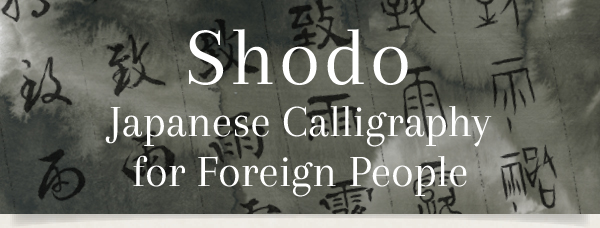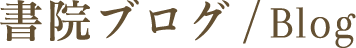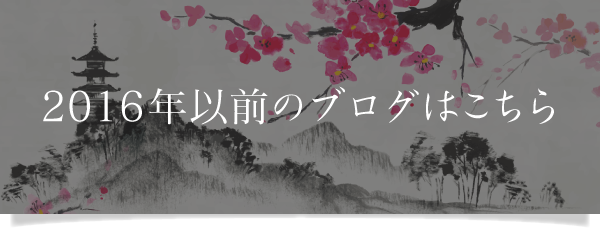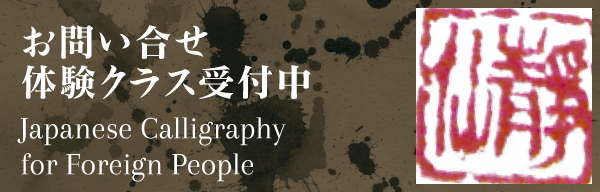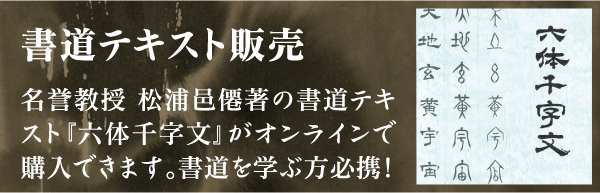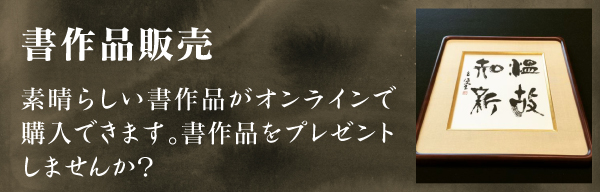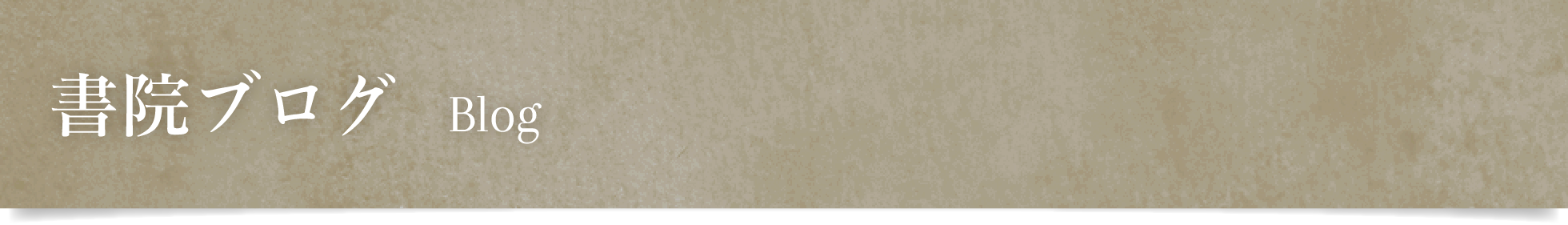
千字文の読み方と意味#6~ 習い事・お稽古事は西麻布書院へ
きのうのブログの続き、千字文の読み方(音読み)と、読み下し文、そして意味についてご紹介のパート6です。
今日は183~216です。
183~196
索居閒處(サクキョカンショ)沈默寂寥(チンモクセキリョウ)
さくきょかんしょし、ちんもくしてせきりょうたり。
人里離れた所に住み、物静かに暮らす。世事には口を出さず俗人と交わらずひっそりと暮らす。
求古尋論(キュウコジンロン)散慮逍遙(サンリョショウヨウ)
いにしえをもとめてじんろんし、りょをさんじてしょうようとす。
昔の人の思想を論じたり、自然の中を心のままにぶらぶらと歩く。
欣奏累遣(キンソウルイケン)慼謝歡招(セキシャカンショウ)
よろこびいたりてわずらいさり、うれいさりてよろこびまねく。
喜ばしい気持ちで心が満たされれば悩みや憂いは去り、楽しいことが自然に招かれるように集まる。
渠荷的歷(キョカテキレキ)園莽抽條(エンポウジョウジョウ)
きょかはてきれきとして、えんぽうはえだをぬきんず。
溝には蓮の花が鮮やかに咲き、庭園の草葉は生い茂り、木々の枝は豊かに伸びる。
枇杷晚翠(ビワバンスイ)梧桐早凋(ゴトウソウチョウ)
びわはおそくみどりに、ごとうははやくしぼむ。
枇杷は冬になっても青々とした葉をつけている。桐は秋には早々と葉は萎れ落ちる。
陳根委翳(チンコンイエイ)落葉飄颻(ラクヨウヒョウヨウ)
ちんこんはいえいし、らくようはひょうようたり。
古い根はしぼみ枯れ、落ち葉は散って風のままに舞っている。
遊鵾獨運(ユウコンドクウン)凌摩絳霄(リョウマコウショウ)
ゆうこんはひとりめぐり、こうしょうをりょうます。
大鳥が一羽、天空のはるか高みを悠々と舞い飛んでいる。
197~216
耽讀翫市(タンドクガンシ)寓目囊箱(グウモクノウソウ)
たんどくいちにもてあそび、めをのうそうにぐうす。
街に出ては書物を読み耽り、家にあっては袋や箱に収められた書物に注目し、ひたすら学問に励む。
易輶攸畏(イユウユウイ)屬耳垣墻(ショクジエンショウ)
いゆうはおそるるところ、みみをえんしょうにつく。
軽率になることはとかく畏れ慎むべきである。生垣や壁には耳がある。
具膳飡飯(グゼンサンハン)適口充腸(テキコウジュウチョウ)
ぜんをそなえはんをくらう。くちにかないちょうにみつ。
食事は礼儀正しく膳を据えて行うべき。食べ物が口に合い、腹がふくれればよく、ご馳走を食べるに及ばない。
飽飫烹宰(ホウヨホウサイ)飢厭糟糠(キエンソウコウ)
あきてほうさいにもあき、うえてはそうこうにもたる。
人は満腹の時はいかにおいしい煮物でも肉料理でも食べることはできないが、飢えたときには米や麦の粕や糠でも食べる。
親戚故舊(シンセキコキュウ)老少異糧(ロウショウイリョウ)
しんせきこきゅう、ろうしょうりょうをことにす。
親戚や古くからの知己とは往来音信するべきである。老人には消化のよい栄養のある食事を与え、若者には粗末な食事でよい。
妾御績紡(ショウギョセキボウ)侍巾帷房(ジキンイボウ)
しょうはせきぼうをぎょし、いぼうにじきんす。
女の人は家内で糸を紡いで家事をし、閨(ねや)をつとめて夫に仕える。
紈扇圓潔(ガンセンエンケツ)銀燭煒煌(ギンショクイコウ)
がんせんはえんにしてけつ、ぎんしょくはいこうなり。
白い絹地のうちわは丸く、銀製の燭台には灯火が光り輝いている。
晝眠夕寐(チュウミンセキビ)藍笋象床(ランジュンショウショウ)
ひるにねむりゆうべにいぬ、らんじゅんぞうしょう。
昼寝をし、夜も眠る。時に若竹で作った藍色のむしろを敷物としたり、象牙で飾った寝台で眠る。
絃歌酒讌(ゲンカシュエン)接盃舉觴(セツハイキョショウ)
げんかしゅえんし、はいをまじえしょうをあぐ。
琴や琵琶をひき、歌い酒宴を催し、語り合い、杯を交わし、乾盃を重ねて宴を楽しむ。
矯手頓足(キョウシュトンソク)悅豫且康(エツヨシャコウ)
てをあげあしをふみ、えつよしてかつやすし。
手を振り上げ足踏み鳴らし、飛び跳ねて舞うことは喜びかつ心安まるものである。
いかがでしたでしょうか。
あと一息。次回が最終回です。(^.^)
西麻布書院 代表 古川静仙
Seisen Furukawa / Head of Nishi-Azabu Shodo Studio
前回の143~182はこちら | この続き217~250(最終回)はこちら
習い事・お稽古事がしたくなったら…西麻布書院へ
- 2026.01.26
- 仮名作品 ~Japanese Kana~
- 2026.01.26
- 書作品用の紙を販売します
- 2024.12.05
- 外国人の書道体験 ~Shodo for foreign people~
- 2022.10.21
- 展覧会作品 ~Shodo exhibition in Ginza!~
- 2022.09.18
- 古川静仙 古筆の臨書~曼殊院本古今集~ ~Furukawa Seisen's journe...

書道教室の西麻布書院は、趣味として学びたい方から本格的に学びたい方まで、書道を基礎からきちんと学べる教室です。ご希望の方は第一回目のクラスを入会手続き前に体験できます。外国人の方には英語でお教えします。出張書道教室もあります。
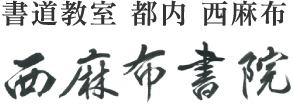
Copyright © Nishi-Azabu Shodo Studio.