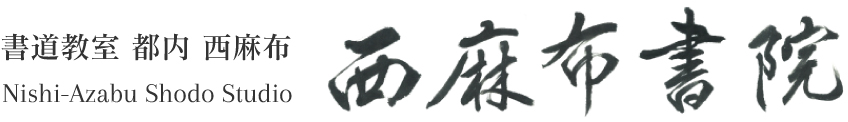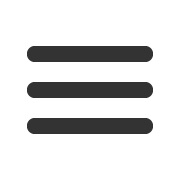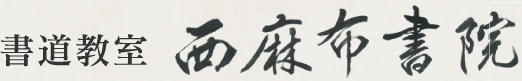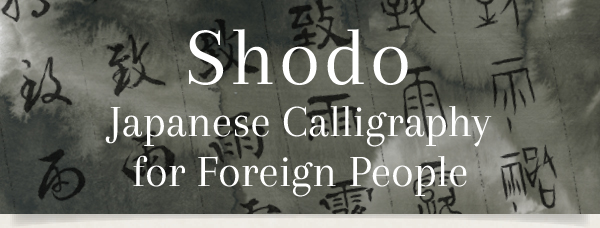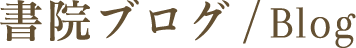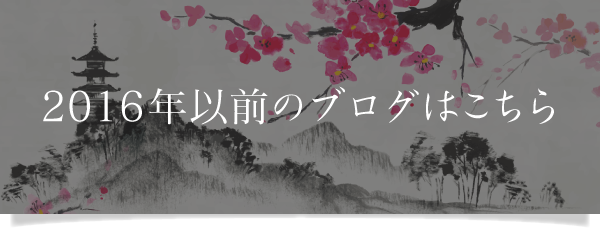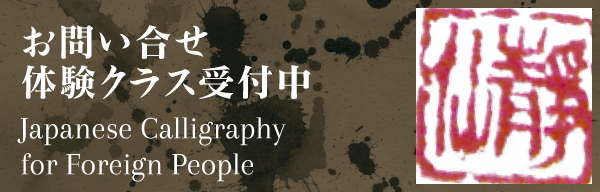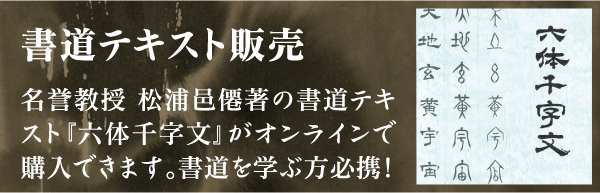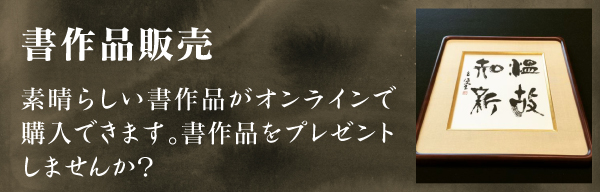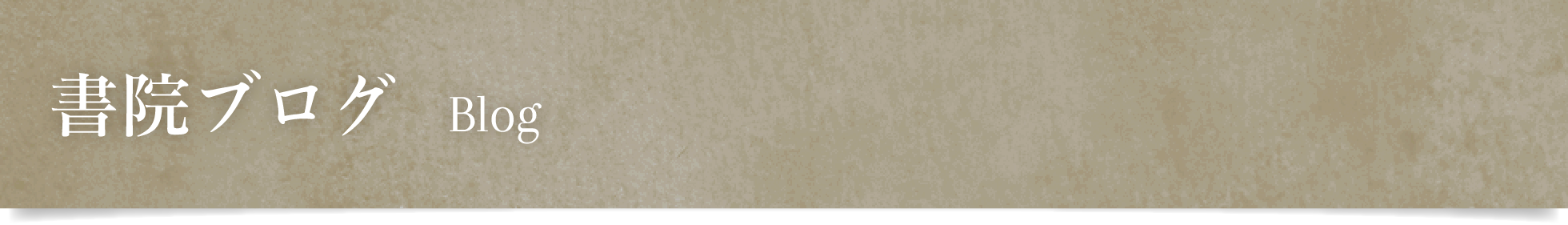
千字文の読み方と意味#5~ 習い事・お稽古事は西麻布書院へ
きのうのブログの続き、千字文の読み方(音読み)と、読み下し文、そして意味についてご紹介のパート5です。
今日は143~182です。
143~162
晉楚更霸(シンソコウハ)趙魏困橫(チョウギコンオン)
しんそはこもごもにはたり、ちょうぎはおうにくるしむ。
晋と楚はともに強国で代わる代わる覇を競い、趙と魏は秦の脅威に苦しめられていた。
假途滅虢(カトメツカク)踐土會盟(センドカイメイ)
みちをかりてかくをほろぼし、せんどにかいめいす。
晋は虞(ぐ)の道を借りて領土を通過し虢(かく)の国を滅ぼし、その帰路虞も滅ぼした。その子文公は諸侯を集め盟約を結ばせた。
何遵約法(カジュンヤクホウ)韓弊煩刑(カンヘイハンケイ)
かはやくほうにしたがい、かんははんけいにやぶる。
漢の蕭何(しょうか)は秦を破った時、簡素な法律を施行した。これに対し韓の韓非子は煩わしい刑法を施行したため民心が離れ国が滅びた。
起翦頗牧(キセンハボク)用軍最精(ヨウグンサイセイ)
きせんとはとぼくとは、ようぐんにさいせいす。
秦の名将白起と王翦(おうせん)、廉頗(れんぱ)と李牧(りぼく)の四将は、軍を率いるに最も精通した武将の代表的な者だ。
宣威沙漠(センイサバク)馳譽丹青(チヨタンセイ)
いをさばくにのべ、ほまれをたんせいにはす。
名将たちは砂漠の匈奴の侵入にもよく闘い勇名を轟かせた。死後も壁画に描かれ名声は馬が駆けるように伝わった。
九州禹跡(キュウシュウウセキ)百郡秦并(ヒャクグンシンヘイ)
きゅうしゅうはうのあと、ひゃくぐんはしんあわす。
禹(う)が中国を九州に分け、秦が百郡を併合し天下を統一した。
嶽宗恆岱(ガクソウコウタイ)禪主云亭(ゼンシュウンテイ)
がくはこうたいをそうとし、ぜんはうんていをしゅとす。
山は恒(こう)山と泰山を尊宗した。祭天の儀は泰山の麓にある云(うん)亭の二山を第一にした。
雁門紫塞(ガンモンシサイ)雞田赤城(ケイデンセキジョウ)
がんもんとしさいと、けいでんとせきじょうと、
北辺の要地に雁門山と万里の長城がある。雞田と赤城は北境にある。
昆池碣石(コンチケッセキ)鉅野洞庭(キョヤドウテイ)
こんちとけっせきと、きょやとどうていと、
山沢湖沼としては昆明の池、碣石(けっせき)山、広大な鉅野(きょや)の湿地、洞庭湖があげられる。
曠遠緜邈(コウエンメンバク)巖岫杳冥(ガンシュウヨウメイ)
こうえんめんばくとして、がんしゅうようめいたり。
これらの原野、湖沼はか遠くに広がり、広大な山々も遥かかなたにほのかに見えるだけである。
163~182
治本於農(チホンヨノウ)務茲稼穡(ムシカショク)
ちはのうをもととす、これかしょくにつとめよ。
国を治める根本は農業である。種をまき収穫するまでこれに努めることだ。
俶載南畝(シュクサイナンポ)我藝黍稷(ガゲイショショク)
ことをなんぽにはじめ、われしょしょくをうう。
南に面した日当たりのよい畑で耕作を始めた。きび、あわを植え付けて農業に励んだ。
稅熟貢新(ゼイジュクコウシン)勸賞黜陟(カンショウチュッチョク)
じゅくをみつぎしんをみつぎ、かんしょうしちっちょくす。
穀物を租税として納め新しい五穀を貢ぐのは農民の務め。よく納める者には賞をもって励まし、怠る者には罰を与える。
孟軻敦素(モウカトンソ)史魚秉直(シギョハイチョク)
もうかはそをたっとび、しぎょはちょくをとる。
孟子は人の善を愛した。史魚(しぎょ)は正直一途に生き、君に従えず自害するという直な人であった。
庶幾中庸(ショキチュウヨウ)勞謙謹敕(ロウケンキンチョク)
ちゅうようをしょきし、ろうけんきんちょくにす。
願わくば人は偏らず、功があっても驕らず、自らを慎み戒めて生きたいものだ。
聆音察理(レイインサツリ)鑑貌辨色(カンボウベンショク)
おとをきいてりをさっし、かたちをみていろをわきまう。
人の話しを注意深く聞いて真意を知り、顔を観察して感情の動きを知ることだ。
貽厥嘉猷(イケツカユウ)勉其祗植(ベンキシショク)
そのかゆうをつたえ、そのししょくをつとむ。
よい考えを子孫に残す。ただそのために慎み深く勉める。
省躬譏誡(セイキュウキカイ)寵增抗極(チョウゾウコウキョク)
みをかえりみてきかいし、ちょうませばこうきょくす。
自らの行いを省みていましめることが大切だ。栄誉を得れば驕り高ぶるので、十分に身を慎むべきである。
殆辱近恥(タイジョクキンチ)林皋幸即(リンコウコウソク)
はじにちかくはじにちかづかば、りんこうにつくことをねがう。
高位に昇るほど人から妬まれて恥辱を受けることが多くなる。その時は好機を見て引退し、山林や湖沼に囲まれた閑静な所へ退きたいものだ。
兩疏見機(リョウソケンキ)解組誰逼(カイソスイヒョク)
りょうそきをみる。そをときてたれかせまらん。
疏広(そこう)と疏受(そじゅ)の父子は士官後身を引く時機とみて官職を辞して故郷に帰った。誰かが迫ったものでもなく、機を見ての勇退であった。
いかがでしたでしょうか。
もう一息です。ではまた次回。(^.^)/
西麻布書院 代表 古川静仙
Seisen Furukawa / Head of Nishi-Azabu Shodo Studio
前回の103~142はこちら | この続き183~216はこちら
習い事・お稽古事がしたくなったら…西麻布書院へ
- 2026.01.26
- 仮名作品 ~Japanese Kana~
- 2026.01.26
- 書作品用の紙を販売します
- 2024.12.05
- 外国人の書道体験 ~Shodo for foreign people~
- 2022.10.21
- 展覧会作品 ~Shodo exhibition in Ginza!~
- 2022.09.18
- 古川静仙 古筆の臨書~曼殊院本古今集~ ~Furukawa Seisen's journe...

書道教室の西麻布書院は、趣味として学びたい方から本格的に学びたい方まで、書道を基礎からきちんと学べる教室です。ご希望の方は第一回目のクラスを入会手続き前に体験できます。外国人の方には英語でお教えします。出張書道教室もあります。
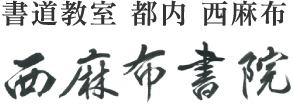
Copyright © Nishi-Azabu Shodo Studio.