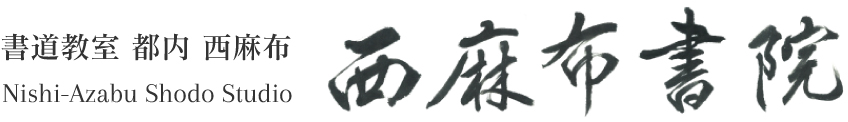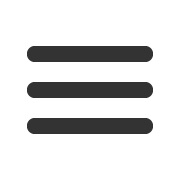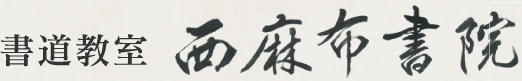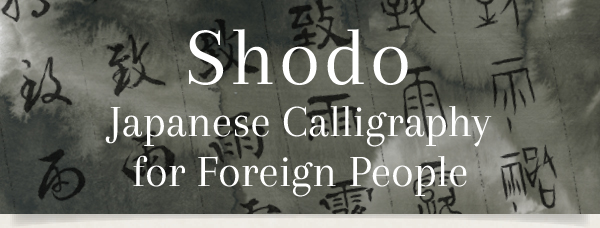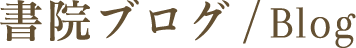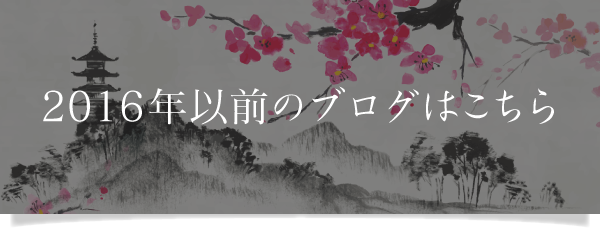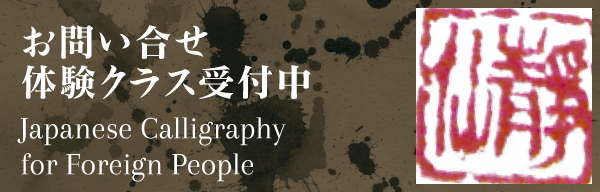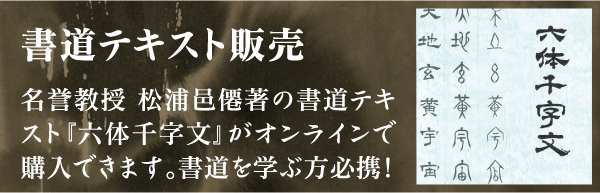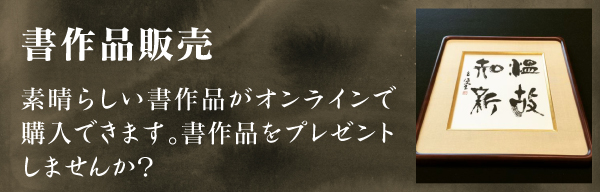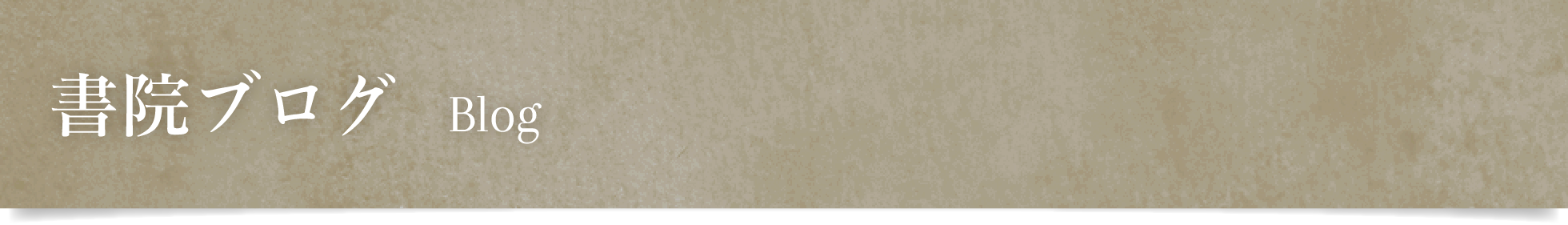
千字文の読み方と意味#2~ 習い事・お稽古事は西麻布書院へ
きのうのブログの続き、千字文の読み方(音読み)と、読み下し文、そして意味についてご紹介のパート2です。
今日は37~68です。
37~50
蓋此身髮(ガイシシンパツ)四大五常(シダイゴジョウ)
けだしこのみとかみは、しだいごじょうなり。
思うに我が身体髪膚(しんたいはっぷ)。身は地水火風の四大から成り、心には仁義礼智信の五常を備える。
恭惟鞠養(キョウイキクヨウ)豈敢毀傷(キカンキショウ)
うやうやしくきくようをおもい、なんぞあえてきしょうせん。
我が身を育てた父母の思いを忘れこの身体を痛め傷つけることがあろうか。
女慕貞絜(ジョボテイケツ)男效才良(ダンコウサイリョウ)
おんなはていけつをしたい、おとこはさいりょうにならえ。
女は心清く正しい行い心がけよ。男は才智を伸ばして才徳のある人間になれ。
知過必改(チカヒツカイ)得能莫忘(トクノウバクボウ)
あやまちをしらばからなずあらため、のうをえてはわするるなかれ。
己の過失に気付いたら必ず改め、習得したことは忘れるなかれ。
罔談彼短(ボウダンヒタン)靡恃己長(ビジキチョウ)
かれのたんをかたるなかれ。おのれのちょうをたのむなかれ。
人の短所は吹聴してはならない。自分の長所に奢り高ぶってはならない。
信使可覆(シンシカフク)器欲難量(キヨクナンリョウ)
まことはふくすべからしめ、うつわははかりがたからんことをほっす。
約束ごとは必ず守り、己の器量は他人に量り難いようにしておく。
墨悲絲染(ボクヒシセン)詩讚羔羊(シサンコウヨウ)
ぼくはいとのそまるをかなしみ、しはひつじをさんす。
墨翟(ぼくてき)は糸を染めるを見て人の心も悪に染まりやすいことを憂いた。詩経は官吏も質素な子羊の皮ごろもを着たと讃えた。
51~68
景行維賢(ケイコウイケン)克念作聖(コクネンサクセイ)
おおいにおこなうはこれかしこく、よくおもうはせいとなる。
立派な行いを積む人は賢人であり よく人の道を思念する人は聖人となる。
德建名立(トクケンメイリツ)形端表正(ケイタンヒョウセイ)
とくたてばなたち、かたちただしければかげただし。
徳を施す者は名を成す。形正せば影も正しい。
空谷傳聲(クウコクデンセイ)虛堂習聽(キョドウシュウチョウ)
くうこくにこえをつたえ、きょどうにきくをならう。
大いなる谷に声が響き渡るように静室に音が伝わる。君子が善言を出すときは諸人はこれに服する。
禍因惡積(カインアクセキ)福緣善慶(フクエンゼンケイ)
わざわいはあくのつむにより、さいわいはよきことのよろこびによる。
悪行の積み重ねが災い招き、善行積めば幸い来る。
尺璧非寶(セキヘキヒホウ)寸陰是競(スンインシキョウ)
せきへきはたからにあらず、すんいんはこれきそう。
聖人は一尺の玉(ぎょく)を宝として尊ぶより、寸時を重んじる。時は得難く失い易いから。
資父事君(シフジクン)曰嚴與敬(エツゲンヨケイ)
ちちにとりてきみにつかう、いわくたっとびうやまうとなり。
父に仕えるのと同じ心で君に仕える。これ尊厳と敬愛をいう。
孝當竭力(コウトウケツリョク)忠則盡命(チュウソクジンメイ)
こうにはまさにちからをつくすべく、ちゅうにはすなわちいのちをつくすべし。
父母には心力の限りを尽くして孝行すべし。君主には命の限り忠義を捧げて仕えよ。
臨深履薄(リンシンリハク)夙興溫凊(シュクコウオンセイ)
ふかきにのぞみうすきをふむごと、つとにおきてあたためすずしくす。
忠孝の道を尽くすことは深い淵に望むように薄氷を履む時のように仕えよ。朝早起きし冬は寝床を温め夏は涼しいよう心配りをせよ。
似蘭斯馨(ジランシケイ)如松之盛(ジョショウシセイ)
らんににてこれかんばしく、まつのさかんなるがごとし。
蘭の香りに似るを目指して道を修め徳を立てよ。松が色を変えないようにその誉は讃えられるであろう。
いかがでしたでしょうか。
まだまだ続きます。また次回。(^.^)
西麻布書院 代表 古川静仙
Seisen Furukawa / Head of Nishi-Azabu Shodo Studio
前回の1~36ははこちら | この続き69~102はこちら。
習い事・お稽古事がしたくなったら…西麻布書院へ
- 2026.01.26
- 仮名作品 ~Japanese Kana~
- 2026.01.26
- 書作品用の紙を販売します
- 2024.12.05
- 外国人の書道体験 ~Shodo for foreign people~
- 2022.10.21
- 展覧会作品 ~Shodo exhibition in Ginza!~
- 2022.09.18
- 古川静仙 古筆の臨書~曼殊院本古今集~ ~Furukawa Seisen's journe...

書道教室の西麻布書院は、趣味として学びたい方から本格的に学びたい方まで、書道を基礎からきちんと学べる教室です。ご希望の方は第一回目のクラスを入会手続き前に体験できます。外国人の方には英語でお教えします。出張書道教室もあります。
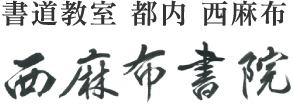
Copyright © Nishi-Azabu Shodo Studio.